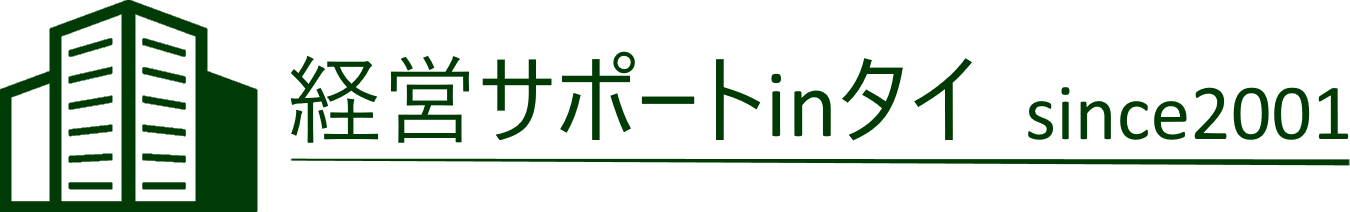日本とタイでは、公証制度や公正証書にあたる文書の仕組みが大きく異なります。
日本の公証制度
日本では、公証役場という国家機関に所属する『公証人』が公正証書の作成や認証業務を行っています。公証人は主に元裁判官や検察官など法務の経験を積んだ人物で、作成される公正証書は非常に高い証明力を持ちます。特に、金銭支払い義務などについて「直ちに強制執行に服する」という文言を入れた公正証書は、裁判を経ることなく強制執行が可能であり、契約不履行時にはそのまま差押えなどの手続きに進めるのが大きな特徴です。このため日本では債権回収や金銭貸借契約の安全性を高める手段として公証役場による公証制度が広く利用されています。
タイの公証制度
一方、タイでは日本のような国家運営の公証役場は存在せず、『Notarial Services Attorney(公証業務弁護士)』という資格を持つ弁護士が 日本でいう公証人に相当する役割を担っています。この資格はタイ弁護士会が付与するもので、契約書や委任状、宣誓供述書などの署名認証や文書の真正証明を行うことはできますが、日本の公正証書のように裁判を省略して強制執行に進める効力はありません。
タイ国内で契約を強制執行可能な形にするには、相手が履行しなかった場合に裁判を起こし、判決や和解調書を得る必要があります。つまり、タイにおける公証とは文書の信頼性を担保することが主な役割であり、直接的な執行力は持たないという点で日本と大きく異なります。
まとめ
このように、日本の公正証書は契約内容の履行を強制するための実効性が非常に高い制度ですが、タイの公証はあくまで文書認証にとどまり、実際の回収や履行確保には別途裁判手続きが必要となります。そのため、同じ「公証」という言葉を使っても、両国では制度の性質と活用方法が大きく異なるのです。