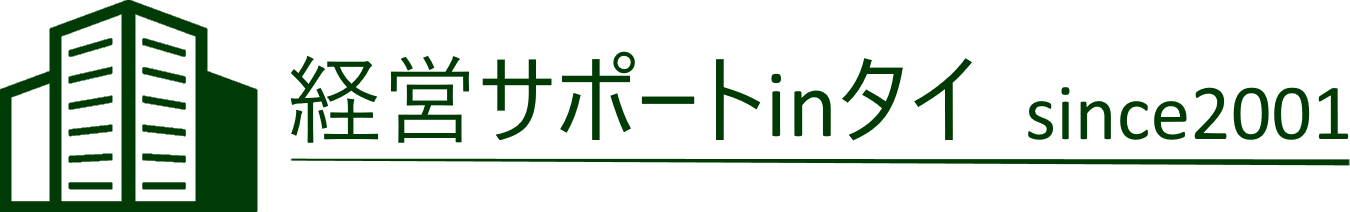民事裁判で借金返済の判決を勝ち取ったにもかかわらず、被告が支払いに応じないというケースは少なくありません。このような場合、判決を得た原告側としては、「強制執行」という手続きを通じて、被告の財産、特に銀行口座を差し押さえるという手段を取ることが可能です。
相手の銀行口座を知っていなくてはならない
しかしながら、実際に差し押さえを行うには、まず被告の銀行口座の所在を把握しておく必要があります。つまり、どの銀行に口座があり、その支店はどこで、口座番号は何かといった具体的な情報を原告側で掴んでおく必要があるのです。
裁判所から開示命令を出してもらえる?
では、そのような情報をどうやって調べればよいのでしょうか。中には、「裁判所から開示命令を出してもらえば、銀行がすぐに口座情報を開示してくれるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際にはそう簡単ではありません。
「官公庁情報公開法」の活用は?
まず、1997年に施行された「官公庁情報公開法」の活用についてですが、これに基づいて判決後に銀行預金の情報を取得することはできません。この法律が適用されるのは、政府が関与する一部の銀行、すなわち政府系銀行や国営企業の銀行に限られており(同法第4条)、一般の民間銀行は対象外となっているからです。
銀行口座は開示しなくてもよい情報
さらに、情報公開の対象となる政府系銀行であっても、債務者の口座情報が開示されるわけではありません。これは同法第15条に基づき、預金口座情報が「開示しなくてもよい情報」とされているためです。
情報公開委員会の判断
実際に、情報公開委員会の判断(案件番号ソーコー129/2550)でも次のように結論づけられています。判決を得た原告が、債務者の口座情報(口座番号や支店名、残高など)を知りたいと要求しても、それは原告の事業上の債権回収活動に過ぎず、個人情報の正当な開示理由には該当しないとされました。加えて、1962年商業銀行法によって、銀行は顧客の情報を第三者に漏らしてはならないと明記されており、この規定は国営銀行にも適用されます。
したがって、裁判所からの開示命令によって銀行口座の情報を取得することはできず、いわゆる「銀行口座調査命令(Subpoena/Submission Order)」の申請も認められていません。
原告側自身で情報を把握する必要がある
以上のような背景から、実際に銀行口座を差し押さえる強制執行の手続きを行うには、原告側自身で被告の銀行名や口座番号といった情報をあらかじめ把握しておく必要があるのです。
あきらめてしまう前に
私たちの事務所では上述したように簡単にはいかない銀行口座の調査を行うことが出来るケースもあります。相手が返済に応じず、実際に強制執行による差し押さえを視野に入れている場合は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
是非弊社へお問い合わせください。
お困りごと、ご相談

ご相談無料です。どうすればよいかの方針をアドバイスさせていただきます。
担当者が可能な限り迅速に返信致します。