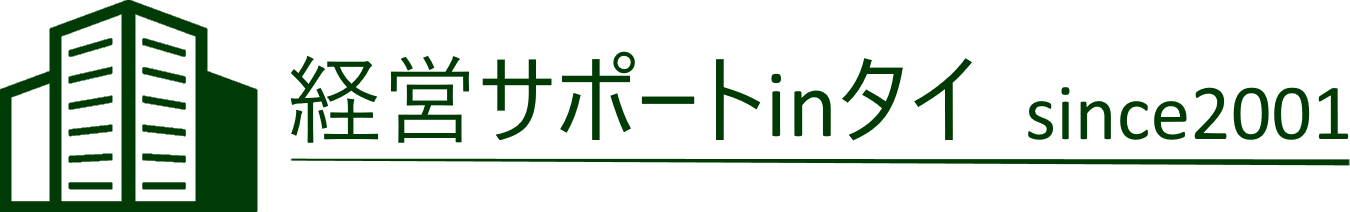タイにおける刑事訴訟は、日本とは制度や運用が異なる点が多く、特に企業関係の詐欺や横領といった経済犯罪に関しては、注意すべきポイントが数多くあります。こうした犯罪が発生した場合、タイの警察や検察、裁判所によって刑事手続が進められることになりますが、対応を誤ると企業としての信用や財産、さらには経営そのものに深刻なダメージを受けかねません。
企業内での詐欺や横領が疑われる場合、まずは内部調査や監査を通じて事実関係を把握することが重要ですが、一定の証拠がそろった段階で、警察への被害届や告訴状の提出を検討することになります。タイでは、被害者が明確な証拠をもって警察に訴えることが非常に重要とされており、初動の対応次第で捜査の進行やその後の刑事訴追に大きな影響を及ぼします。証拠が不十分であったり、提出が遅れたりすると、捜査が行われないまま事件が立ち消えになることもあります。
ですので、通常は証拠集めの段階から専門家へご相談することが最適な手順と思われます。
警察が捜査を開始すると、関係者への事情聴取、関係資料やデジタルデータの押収、必要に応じた被疑者の逮捕や勾留などの措置が取られることがあります。特に企業で起こる不正行為では、複数人が関与していたり、証拠隠滅の恐れがある場合も多いため、警察側も慎重かつ広範囲に捜査を進めます。
その後、事件が検察に送致されると、検察官が起訴するかどうかを判断します。タイでは、検察官が独自に判断して不起訴とすることもありますが、被害者がこの判断に不服を持つ場合、上級の検察官への不服申し立てや、場合によっては民事訴訟などを通じた補償請求へと進むケースもあります。また、示談が成立した場合には、加害者の不起訴処分や量刑の軽減につながることもあります。
刑事訴訟が開始されると、裁判は第一審から始まり、検察官による立証活動、被告人や証人の供述、被害者からの意見陳述などが行われます。企業犯罪では、被害額や不正の手口、被告人の立場などが重要な争点となり、場合によっては社内資料や会計記録、電子メールのやり取りなどが証拠として提出されることになります。裁判所はこれらの証拠を総合的に判断し、有罪か無罪かを決定します。
なお、タイでは刑事事件の処分が下るまでに時間がかかる傾向があり、特に複雑な経済犯罪事件では数年単位にわたる訴訟となることもあります。その間、企業としては再発防止策や社内対応の見直しを迫られる場面も多く、同時に社会的信用の回復に向けた取り組みが必要になることもあります。
また、加害者が企業の内部者である場合、刑事手続とは別に、雇用契約上の処分や損害賠償請求の問題も並行して発生します。刑事と民事の両面で対応を進めるには、タイ法に精通した専門の弁護士と連携しながら、適切な戦略をとることが極めて重要です。企業として刑事事件に関与することになった場合、被害者であっても加害者であっても、法的リスクの把握と迅速な対応が、その後の企業活動に大きく影響することを理解しておく必要があります。