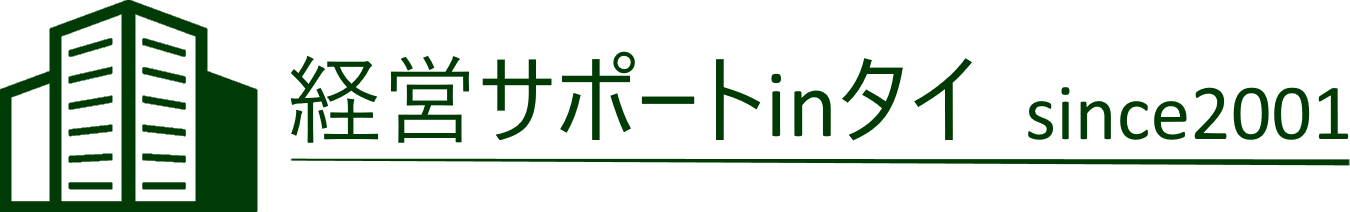タイにおける解雇問題は、企業の評判やコスト、さらには法的リスクに直結する重大な事案です。そのため、トラブルを未然に防ぐための事前対応が極めて重要となります。
「正当な理由」と「証拠」の存在が不可欠
まず、解雇にあたっては「正当な理由」と「証拠」の存在が不可欠です。何の理由もなく、あるいは口頭のみで解雇を通告することは、後に不当解雇として訴えられる大きなリスクを孕んでいます。
したがって、解雇を行う場合は、勤怠の著しい不良や業績の不振、重大な就業規則違反といった客観的かつ合理的な理由を明示し、それを裏付ける証拠を文書で残しておく必要があります。
特に、事前に書面による警告書(Warning Letter)を交付し、従業員に改善の機会を与える対応が望まれます。また、メールや報告書、業務評価記録などの内部文書も証拠として整理・保管しておくことが求められます。
「懲戒解雇」と「普通解雇」の違い
ここで注意すべきなのが、「懲戒解雇」と「普通解雇」の違いです。
懲戒解雇とは、従業員が重大な不正や違法行為、会社の規則に対する深刻な違反を行った場合に、企業が即時に解雇できる制度を指します。この場合には、事前通知や解雇補償金の支払い義務はありません。ただし、正当な懲戒解雇と認められるためには、解雇の理由を記載した通知を発行しなければならず、かつその内容を裏付ける明確な証拠が求められます。つまり、法律上の要件を厳格に満たす必要があります。
一方、普通解雇は、企業の経営判断や人員整理、あるいは能力不足などを理由として行う一般的な解雇(雇用契約終了)のことを指します。従業員側に重大な落ち度があるわけではないため、原則として事前の通知または通知手当の支払いが必要となり、加えて勤務年数に応じた解雇補償金の支払いも義務付けられます。
2つは大きく異なる
このように、懲戒解雇と普通解雇では、解雇理由の性質や企業側の義務、従業員に与える影響が大きく異なるため、状況に応じた慎重な判断が求められます。
解雇に際しての「事前通知」
タイの労働法では、解雇に際して「30日前の通知」または「通知に代わる予告手当(payment in lieu of notice)」の支払いが原則とされています。
これは、従業員に対して事前に書面で雇用終了を通知しなければならないというルールであり、通知後の30日分の給与、もしくは給料支払い期間に相当する金額を支払うことが義務となっています。
ただし、従業員が重大な不正行為や違法行為を行った場合には、懲戒解雇として即時解雇が認められる例外も存在しますが、そのような正当な理由がない限り、上記の通知や手当の支払いが必要です。
「解雇補償金」の支払い義務
従業員に過失がない解雇の場合(普通解雇)には、法律により勤続年数に応じた「解雇補償金」の支払い義務が生じます。
2024年時点の基準によれば、勤続期間が120日未満であれば補償金の支払いは不要ですが、それ以上の場合は退職時の賃金に基づき、30日分から最大400日分の範囲で支払う必要があります。例えば、勤続が10年を超える従業員を解雇する場合には、300日分以上、20年以上の場合には400日分以上の補償が求められることになります。
注:解雇補償金以外にも上述の「通知に代わる予告手当」が必要になるケースが多い
契約社員の契約終了について
勘違いされることが多いのが、「契約社員」の解雇の場合です。
例えば、「1年間の契約社員」として雇用して契約期間が終わった場合、120日以上の雇用をしておりますので、退職時の賃金の30日分以上の解雇補償金の支払い義務があります。
契約終了でも解雇補償金の支払いは必要
「契約を区切っていたので解雇ではなく、契約終了だ」として解雇補償金を支払わない企業が見受けられますが、タイではこのようなケースでも解雇補償金の支払い義務があります。
報復的解雇は不当解雇
妊娠中の従業員や、労働組合活動、内部通報を行った従業員を解雇することは、差別的あるいは報復的解雇として違法と判断される可能性が高く、企業にとって非常に大きなリスクとなります。
タイの裁判所もこれらの事案には厳格な姿勢で臨んでおり、違法と判断された場合には高額な損害賠償が命じられることもあります。
外国人(日本人)従業員の解雇
日本人を含む外国人従業員(Expat)の解雇に関しては、ビザや労働許可証(Work Permit)の有効性とも関係してくるため、特に注意が必要です。
雇用終了と同時にこれらの資格も無効となるため、手続きの不備が出国トラブルにつながることもあります。適切な通告期間の確保や、出国までの猶予措置、文書による通知の実施などを慎重に行うことが求められます。
労働紛争に発展するケースも
解雇は企業にとって最後の手段であり、実施にあたっては就業規則や労働契約の内容、過去の評価記録などを十分に確認した上で、法務部や弁護士と事前に協議することが望まれます。
なぜなら、労働紛争においては企業側が防御的立場となることが多く、証拠の整合性や手続きの適正さが強く問われるからです。
万が一、労働争議に発展した場合には、裁判外での和解や補償金支払いによる早期解決も常に検討すべき選択肢です。実務上は、労働省や労働裁判所での調停制度(conciliation)を利用することも効果的であり、これにより訴訟に発展する前の段階で問題を解消することが可能となります。
重要なのは常日頃の準備(就業規則、懲戒規定)
最後に、従業員の行為が明確に「違反」と認定されるためには、企業としての就業規則や懲戒規定がしっかり整備され、全従業員に周知されている必要があります。
内部ルールが曖昧なままでは、いざという時に適切な対応が難しくなり、企業側の立場が不利になる恐れもあるため、日頃からの整備と運用の徹底が重要です。
従業員の解雇が発生する場合、法律的な不安がある場合には、
是非弊社へお問い合わせください。
お困りごと、ご相談

ご相談無料です。どうすればよいかの方針をアドバイスさせていただきます。
担当者が可能な限り迅速に返信致します。